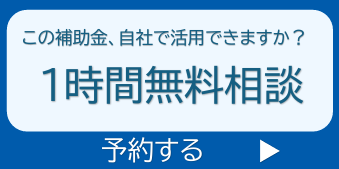研究開発税制と補助金の併用は可能?圧縮記帳との違いとシミュレーション解説
※本コラムでは、研究開発税制や圧縮記帳などの制度を一般的に紹介しています。
具体的な適用可否や節税額の試算は、税理士にご相談ください。
企業の成長に欠かせないのが研究開発投資です。しかし、新技術や新製品の開発には多額のコストがかかり、資金面での負担が大きな課題となります。こうした課題に対応するため、国は「補助金」と「税制優遇」という二つの支援策を用意しています。その中でも「研究開発税制」は、法人税額から直接控除できる強力な仕組みであり、主要補助金と組み合わせることでメリットを最大化できます。
本記事では、研究開発税制の基本から、主要補助金との併用の考え方、さらに数値シミュレーションを通じて実務に役立つポイントを解説します。
税制の詳細な適用可否については税理士へご確認ください。
補助金活用や事業計画づくりに関するご相談は、当事務所にて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
補助金お問い合わせフォーム
研究開発税制とは?中小企業も使える税額控除制度
研究開発税制とは、企業が行った研究開発費の一部を法人税から直接控除できる制度です。通常の経費処理や減価償却による損金算入とは異なり、支払う税額そのものを減らせるため、資金繰りに与える効果は大きいといえます。
中小企業の場合、研究開発税制の控除率はおおむね試験研究費総額の10%程度(制度改正により変動あり)です。例えば1,000万円の研究開発費を支出した場合、100万円分を法人税額から差し引くことが可能になります。
対象となる研究開発費には以下が含まれます。
- 新製品・新技術のための試作や実験費用
- 大学・研究機関との共同研究費
- 外注先への委託研究費
- 社員の研究開発活動にかかる人件費
主要補助金との関係
研究開発投資を支援する制度としては、補助金も代表的です。特に経済産業省の主要補助金は研究開発型の取り組みと相性が良く、毎年多くの企業が活用しています。
代表例としては以下が挙げられます。
- ものづくり補助金:新製品開発や生産プロセスの改善投資に活用可能 ▶ものづくり補助金解説コラム
- 中小企業省力化投資補助金:AIやロボットなどの導入による生産性向上を支援 ▶中小企業省力化投資補助金解説コラム
- 成長加速化補助金・大規模成長投資補助金:研究開発から実装・事業化までを後押し ▶成長加速化補助金解説コラム、大規模成長投資補助金解説コラム
これらの補助金で対象となる経費の中には、研究開発税制の対象となる費用が含まれるケースがあります。
併用は可能?補助金と研究開発税制の関係
補助金と研究開発税制は、基本的に併用可能です。
ただし、補助金で賄われた部分をそのまま税額控除対象にすることはできません。つまり、自己負担分のみが研究開発税制の対象となります。
たとえば、ものづくり補助金で2/3の助成を受けた場合、残りの1/3を企業が負担します。この自己負担額が研究開発費として税額控除の対象になる仕組みです。
税制の詳細な適用可否については税理士へご確認ください。
補助金活用や事業計画づくりに関するご相談は、当事務所にて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
補助金お問い合わせフォーム
シミュレーションで比較する:研究開発税制の効果
ここでご紹介する内容は、あくまで一般的な制度の仕組みです。
実際の税務処理については、企業の状況によって判断が異なるため、必ず顧問税理士等にご確認ください。
前提条件
総研究開発費:3,000万円
補助金助成率:2/3(補助金 2,000万円、自己負担 1,000万円)
研究開発税制の控除率:10%
補助金なしで研究開発税制の場合
3,000万円自己負担
研究開発税制の控除額 300万円(10%)
補助金ありで研究開発税制の場合
1,000万円自己負担
研究開発税制の控除額 100万円
このように、補助金がある場合は自己負担額が減る分、税額控除額も小さくなります。補助金で大幅にコストを軽減したうえで、さらに残りの部分について税制優遇を受けられるため、資金繰り改善効果は大きいといえるでしょう。
圧縮記帳と研究開発税制の違い
ここで、補助金や助成金に関連してよく議論されるのが「圧縮記帳」との違いです。
圧縮記帳
補助金で取得した固定資産(機械・設備など)の取得価額を圧縮して、税務上の減価償却費を減らす方法。補助金を受けた場合に適用される。
▶補助金と圧縮記帳|どの補助金なら税負担を減らせる?制度ごとの適用可否を解説
研究開発税制
研究開発費に対して法人税額控除を行う制度。補助金の有無に関わらず、対象となる研究開発費に使える。
両者は性質が異なるため、対象が重ならない範囲では併用も可能です。
シミュレーションで比較する:圧縮記帳との併用
シミュレーション:補助金+研究開発税制と圧縮記帳との併用
前提条件
企業規模:中小企業
総研究開発費:2,000万円
設備投資:1,000万円
補助金:ものづくり補助金(一般型・補助率2/3)
研究開発税制控除率(中小企業型):10%
法人税額(研究開発税制適用前):600万円
自己負担額と補助額
自己負担額:1,000 − 666 = 334万円
設備投資1,000万円のうち、補助額666万円(補助率2/3)
研究開発費2,000万円のうち、設備投資分は補助金で賄われたため控除対象外
自己負担の研究開発費:2,000 − 666 = 1,334万円
圧縮記帳の効果
補助金が交付された設備投資分(666万円)は圧縮記帳可能
取得価額を圧縮することで減価償却費を調整し、税務上の課税所得を減らせる
研究開発税制の効果
自己負担の研究開発費1,334万円 × 10% = 133万円の法人税控除
さらに圧縮記帳で将来的に減価償却費を圧縮できるため、短期的にも長期的にも税負担を軽減できる効果があります。
ポイント:補助金+研究開発税制と圧縮記帳との併用
1.補助金で賄われた部分は研究開発税制の対象外
自己負担分だけが控除可能
2.圧縮記帳と研究開発税制は併用可能
圧縮記帳で設備投資分を課税繰延し、残りの自己負担分に税額控除を適用
3.資金繰り効果が最大化
補助金でコストを軽減+残りの自己負担部分を税制で還付
東京都の助成金との関係
東京都の「TOKYO戦略的イノベーション促進事業」などは、圧縮記帳の対象外とされています。前回のコラムで触れた通り、この点は注意が必要です。
▶補助金と圧縮記帳|どの補助金なら税負担を減らせる?制度ごとの適用可否を解説
ただし、研究開発税制については国税庁の制度であり、補助金の種類に関わらず、要件を満たす研究開発費用であれば適用可能です。東京都助成金で設備補助を受けた場合でも、補助金でカバーされない研究開発人件費や材料費については研究開発税制を利用できます。
まとめ
研究開発税制は、補助金と違って「後から法人税額を減らせる」という特徴があり、資金繰りの安定に直結します。特に、
- 補助金を受けた研究開発投資の自己負担分
- 助成金ではカバーされない研究人件費や材料費
といった部分で効果を発揮します。
また、圧縮記帳との違いを理解しておくことで、補助金と税制を組み合わせた最適な節税戦略を立てることが可能です。
補助金を申請する企業は、採択後の税務処理として「圧縮記帳」や「研究開発税制」をどう活用するかまで視野に入れておくと、資金効果を最大化できます。
本記事は制度の概要説明にとどまるものであり、個別の税務判断を行うものではありません。
実際のご利用にあたっては、税理士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
【参考】今後の研究開発税制の傾向や企業に求められる方向性
令和5年度税制改正により、中堅・大企業でも積極的に研究開発投資を行うメリットが増すことが予想されます。
従来の単純な研究開発費控除から、戦略的・質の高い研究開発を後押しする制度へ進化しているといえます。
節税対策について関連コラム
中小企業経営強化税制の活用 ― 即時償却と税額控除、どちらを選ぶべきか?
補助金と圧縮記帳|どの補助金なら税負担を減らせる?制度ごとの適用可否を解説
※税制の詳細な適用可否については税理士へご確認ください。
税制の詳細な適用可否については税理士へご確認ください。
補助金活用や事業計画づくりに関するご相談は、当事務所にて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
補助金お問い合わせフォーム