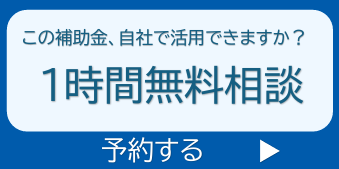中小企業経営強化税制の活用 ― 即時償却と税額控除、どちらを選ぶべきか?
※本コラムでは、中小企業経営強化税制の制度を一般的に紹介しています。
具体的な適用可否や節税額の試算は、税理士にご相談ください。
中小企業が設備投資を行う際に活用できる代表的な制度の一つに「中小企業経営強化税制」があります。
この制度は、生産性向上や経営基盤の強化につながる機械装置やソフトウェアなどを導入した場合に、税制上の優遇措置を受けられるものです。
▶ 中小企業経営強化税制の拡充及び延長についてのコラム(2024.09.03)
優遇措置には大きく分けて 「即時償却」 と 「税額控除」 の二つがあります。どちらを選択するかによって、節税効果や資金繰りへの影響が変わってきます。ここでは、それぞれの仕組みと選び方について詳しく解説します。
ご不明な点やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。
※税制の詳細な適用可否については税理士へご確認ください。
▶ お問い合わせフォームへ
即時償却とは?
即時償却とは、対象となる資産を取得した年度に、その取得価額の全額を経費として計上できる仕組みです。通常であれば数年にわたり減価償却をしていく資産でも、一度に損金算入できるため、その年度の課税所得を大きく減らす効果があります。
たとえば500万円の機械を導入した場合、本来であれば耐用年数に応じて毎年数十万円ずつ償却していきます。しかし即時償却を選択すれば、その500万円を初年度にすべて経費化できるのです。
その結果、利益を圧縮して法人税を軽減できるだけでなく、赤字を回避したり、資金繰りの改善に役立つケースがあります。一方で、償却を前倒ししているだけなので、翌年度以降は償却費がなくなり、その分の節税効果は小さくなる点に注意が必要です。
税額控除とは?
税額控除は、計算された法人税額から一定割合を直接差し引く仕組みです。中小企業経営強化税制では、通常7%(条件によって10%)の税額控除が認められています。
- 資本金3,000万円以下の中小企業では10%
- 資本金3,000万円超~1億円以下の中小企業では7%
仮に500万円の機械を購入した場合、7%であれば35万円を税額からそのまま差し引くことができます。これは「利益を圧縮する」のではなく「納めるべき税金を減らす」制度ですので、即効性があり、利益をしっかり出している会社にとっては大きなメリットがあります。
ただし、控除できる金額には上限があり、法人税額の20%を超えては控除できません。また、赤字や税額が少ない場合には十分に効果を発揮できないという制限もあります。
どちらを選ぶべきか?――即時償却と税額控除
即時償却と税額控除は、どちらが有利か一概に言えるものではありません。会社の利益水準や今後の事業計画によって最適な選択肢は異なります。
- 利益がしっかり出ていて、法人税を多く負担している会社 → 税額控除の方が効果的
- 利益が少なく、赤字転落のリスクがある、あるいは資金繰りを重視したい会社 → 即時償却が有効
また、金融機関への決算内容の見せ方を意識する場合にも、どちらを選ぶかで評価が変わる可能性があります。
ご不明な点やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。
※税制の詳細な適用可否については税理士へご確認ください。
▶ お問い合わせフォームへ
シミュレーション例――即時償却と税額控除
ここでご紹介する内容は、あくまで一般的な制度の仕組みです。
実際の税務処理については、企業の状況によって判断が異なるため、必ず顧問税理士等にご確認ください。
500万円の機械を購入した場合に、利益の状況によってどちらが有利になるかを考えます。
前提条件
- 設備投資:500万円
- 税額控除率:7%(資本金3,000万円超の中小企業を想定)
ケースA:利益1,000万円、法人税額300万円
即時償却の場合
500万円を経費にできるので、課税所得は 1,000万円 − 500万円 = 500万円
法人税は(仮に30%とすると) 150万円
節税効果は「税金300万円 → 150万円」なので 150万円の軽減効果。
税額控除の場合
課税所得はそのまま1,000万円。法人税は300万円
そこから 500万円 × 7% = 35万円控除
税額は 265万円。
節税効果は 35万円
このように、ケースAでは「即時償却(150万円軽減効果)」の方が圧倒的に有利です。
ケースB:利益200万円、法人税額60万円
即時償却の場合
200万円 − 500万円 = ▲300万円(赤字)
法人税は赤字の場合 ゼロ なので、当期の税額は完全に圧縮可能。
節税効果は「60万円 → 0円」なので 60万円の軽減効果
税額控除の場合
課税所得はそのまま200万円で法人税60万円
控除額は 500万円 × 7% = 35万円
税額は 25万円。
節税効果は 35万円。
ケースBでも「即時償却(60万円効果)」の方が有利です。
ケースC:赤字
即時償却の場合
課税所得は ▲100万円 − 500万円 = ▲600万円 となります。
税額は当然ゼロ。
「税金ゼロ」以上には減らせません。
つまり、当期の節税効果はゼロです。
ただし、この「▲600万円」の赤字は税務上「欠損金」として翌年度以降に繰り越せます(繰越欠損金の控除)
翌年度に利益が例えば800万円出た場合を考えます。
繰越欠損金600万円を控除できる。
課税所得=800万円 − 600万円 = 200万円。
翌年の法人税は大幅に軽減されることになります。
税額控除の場合
控除対象の法人税がないため効果なし
このように赤字の場合は、当期は税金ゼロなので効果がありません。ただし即時償却でさらに赤字を増やした分は「繰越欠損金」として将来利益と相殺できるため、将来の節税効果に繋がります。
税額控除が有利になる場合
先ほどのシミュレーション例を見ると、「じゃあどんな時でも即時償却を選べばいいのでは?」と思うのではないでしょうか。
即時償却を選ぶと課税所得を減らすことはできますが、節税効果は「減らした課税所得 × 法人税率」になります。
税額控除は取得価額×控除率で直接税額から減らせるため、法人税率が低い場合や控除率が高い場合には、即時償却よりも節税額が大きくなることがあります。
法人税率が低く、控除率が高い場合
前提条件
- 課税所得:2,000万円
- 法人税率:5%(非常に低い)
- 税額控除率:10%
- 設備投資額:500万円
即時償却の場合
課税所得:2,000 − 500 = 1,500万円
法人税:1,500 × 5% = 75万円
節税効果:2,000 × 5% − 1,500 × 5% = 25万円
税額控除の場合
法人税:2,000 × 5% = 100万円
税額控除:500 × 10% = 50万円
法人税:100 − 50 = 50万円
節税効果:50万円
この場合は、税額控除(50万円)が即時償却(25万円)より有利になります。
資金繰りや会計上の利益との兼ね合いを考える場合
即時償却で利益を大きく圧縮すると、決算書上の利益が少なくなります。
金融機関からの評価や配当計画に影響が出る場合、あえて税額控除を選んで課税所得を圧縮せずに法人税を減らす方が望ましい場合もあります。
このように、即時償却と税額控除は、どちらが有利か一概に言えるものではありません。会社の利益水準や今後の事業計画によって最適な選択肢は異なります。
節税額そのものは即時償却の方が大きくなることが多いですが、利益や会計上の数字、金融評価、控除率などの条件によっては税額控除を選んだ方が望ましい場合もあるのです。
まとめ
中小企業経営強化税制は、設備投資を行う企業にとって強力なサポートとなる制度です。しかし、即時償却と税額控除のどちらを選ぶかによって、効果の出方は大きく異なります。
- 即時償却は、利益圧縮や赤字対策に有効
- 税額控除は、利益が出ている会社に即効性あり
最終的には、自社の決算予測や資金繰り、金融機関との関係性を考慮しながら選択することが重要です。制度を最大限活用するためには、事前に事業計画を立て、顧問税理士や専門家と相談のうえ検討すると安心でしょう。
本記事は制度の概要説明にとどまるものであり、個別の税務判断を行うものではありません。
実際のご利用にあたっては、税理士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
税金の負担を軽くできる可能性がある圧縮記帳についてのコラムはこちら
ご不明な点やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。
※税制の詳細な適用可否については税理士へご確認ください。
▶ お問い合わせフォームへ