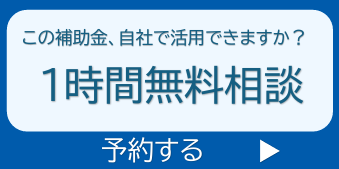中小企業支援の次を読む ― 保証料引き下げ制度と補助金予算の最新動向
中小企業・小規模事業者をめぐる支援制度が、2025年11月時点で新たな局面を迎えようとしています。
例えば、資金調達時の保証料引き下げを検討する制度が動き出しつつあり、また予算面では補正・当初予算が中小企業支援を明確に意識した方向へと進んでいます。
本コラムでは、
①保証料引き下げ制度の現段階でのポイント
②補助金・予算の直近動向から読み解く支援制度の「次のフェーズ」
③専門家として・経営者として備えておくべき観点
を整理します。
保証料引き下げ制度の最新動向
まず動きが活発なのが、信用保証料の引き下げを目指した新制度です。
保証料引き下げ制度とは? ― 背景・具体的な制度案
これは、一般の融資で信用保証協会の保証を受けた場合に企業側が負担する「保証料」を、経済産業省が協会に補助金を出す形で軽減するというものです。
この制度の背景には、コロナ禍で実施されたゼロゼロ融資の返済対応を巡り、金融機関側の把握が十分でないことや、代位弁済(信用保証協会が肩代わりする状況)が増えていることが挙げられます。
具体的な制度案としては、次のような枠組みが想定されています。
- 年4回(3カ月に1回)の経営データ報告が要件
- データ作成は「税理士ら専門家」が支援し、決算書だけでなく、取引先や事業承継の情報も含める見通し
- 保証料引き下げに対する補助は、信用保証協会に対して交付される形を想定
- 2026年3月にも受付開始を目指している
読み取れる今後の傾向は?
企業側にとっては、「保証料が下がる」という直接的メリットと引き換えに、「データを継続的に提出する管理負担」が発生する点には注意が必要です。とはいえ金融機関・税理士・信用保証協会が定期的に情報を共有できることは、資金繰りや経営改善の観点でもプラスに働く可能性があります。
この制度はまだ検討中の段階で詳細は確定していませんが、「日常的に経営データを整理しておくことが前提になる時代」の到来を感じさせます。
今のうちから税理士と連携し、決算書以外の経営指標(取引先の集中度、新規事業の進捗など)も意識してデータ管理の習慣を作っておくことが重要です。
補助金・予算動向:支援制度の次のフェーズを読み解く
補助金・支援制度の予算面でも変化が見られます。
中小企業庁の発表資料によれば、中小企業対策費として
- 令和7年度では1,080億円
- 令和8年度では、1,378億円要求
という数字が示されており、「100億円企業を含む中小企業・小規模事業者の成長に向けた取組を後押しするため、予算・税等の政策手段を総動員する」として打ち出されています。
注目すべきは、この「量」だけではなく、「質」です。すでに概算要求段階でも次のような重点テーマが織り込まれています。
- 省力化設備導入と賃上げをセットにした事業の支援
- 事業承継やM&Aに対する補助制度の拡充
- 脱炭素化やデジタル化への挑戦を前提とした生産性向上策の支援
補助金は「出ること」そのものが注目されがちですが、国としてどの方向に経営を舵取りしてほしいのかというメッセージを的確に読み取ることが重要です。単なる出たから申請する姿勢ではなく、自社が取り組みたい方向性と合致するものを見極める視点も求められます。
ここ数年の補助金は「単に設備導入に補助を出す」のではなく、「賃上げ」「成長」「構造転換」といったテーマとセットになる傾向が強まっています。つまり、支援の質が問われるフェーズに入っており、申請書に書かれる計画の実現性や波及効果も重要になると考えられます。
参考コラム
中小企業補助金はどう変わる?概算要求から見える来年度の方向性―大規模投資補助金はどうなる?
経営者/支援専門家が今押さえておきたい3つの観点
以上を踏まえ、「まだ制度が開始していない現段階だからこそ」、次のような準備が求められます。
① データ・財務整理の体制構築
保証料引き下げ制度のように、経営データの定期提出が求められる制度が増える可能性があります。数字が苦手という理由で後回しにせず、早めに会計や業績管理の仕組みを整えておくことが大切です。
② 支援制度のテーマ動向把握と自社適合性の検証
補助金ごとに重点テーマが異なり、申請に求められる視点も高度化しています。「なんとなく使える補助金」ではなく、「自社の成長戦略に合致した制度」を選ぶ姿勢が重要です。
③ 税理士・行政書士・金融機関との早期連携
制度の動向は、国の発表から現場の周知までタイムラグがあります。信頼できる専門家との連携は、有益な情報を早期にキャッチする点でも、書類作成・事業計画の伴走支援という面でも大きなメリットになります。
当社の中小企業・小規模事業者支援
なお、当社では補助金・資金調達に関する初回相談(1時間)を無料で承っています。
中小企業・小規模事業者の皆さまが「何から手をつければよいか分からない」と感じる段階でも、丁寧に状況をお伺いし、必要に応じて最適な補助金や支援制度のご提案を行います。
※帳簿作成や税務処理など、税理士業務の範囲に該当するご相談は対応できません。その点はご理解いただけますと幸いです。
補助金活用や経営改善計画の立案といったご支援には対応しておりますので、事業の方向性や補助金活用の可能性を整理したい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
保証料引き下げ制度も補助金予算も、「まだこれから」ではありますが、制度の方向性を正しく理解し、日常業務の中でのデータ整理や経営計画の見直しをしておくことが、次のチャンスにつながります。
支援制度は待っているだけでは「聞き逃し」や「出遅れ」が生じます。いま多くの中小企業が求められているのは、「補助金を使う」のではなく、「制度を味方につけて経営を進める視点」です。
専門家としても、制度設計そのものの動向や背景を読み、必要に応じて情報を提供できる体制作りを心がけたいものです。