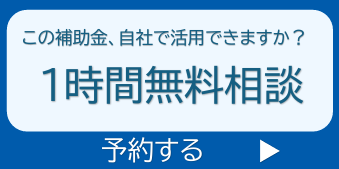補助金にも税金がかかる!?税負担を減らす圧縮記帳とは?
※本コラムでは、圧縮記帳の制度を一般的に紹介しています。
具体的な適用可否や節税額の試算は、税理士にご相談ください。
「補助金をもらったのに、税金まで払わなきゃいけないの?」と思う方も多いかもしれません。 実は、補助金も企業の収益とみなされるため、所得税や法人税の対象になるのです。
しかし、「圧縮記帳」という制度を使えば、税金の負担を軽くできる可能性があります。
税制の詳細な適用可否については税理士へご確認ください。
補助金活用や事業計画づくりに関するご相談は、当事務所にて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
補助金お問い合わせフォーム
圧縮記帳とは?
簡単に言うと、補助金を受け取って購入した設備などの費用を、会計上うまく処理して税金の負担を減らす方法です。
簿記の視点から見ると、補助金は通常「雑収入」や「補助金収入」として収益に計上されます。 そのまま計上すると、所得が増えるため税金がかかってしまいます。
例えば、国や自治体から500万円の補助金をもらった場合、 この500万円を収益に計上すると、その分の法人税が発生します。
しかし、「圧縮記帳」を適用すれば、補助金収入の金額を資産の取得価額から控除できるため、 課税所得を減らすことが可能になります。
圧縮記帳のメリットは?
- 税金の負担を減らせる
収益をそのまま計上すると税金が増えてしまいますが、圧縮記帳を適用すれば課税所得を減らせます。 - 減価償却の調整が可能
直接圧縮法を使えば取得価額が減少するため、減価償却費の計上額も減ります。 - 実際の資金繰りに合った処理ができる
補助金をもらって設備を購入した場合、税金が増えると手元の現金が減ります。 圧縮記帳を使うと、現金の流れに合わせた税負担の調整が可能になります。
税制の詳細な適用可否については税理士へご確認ください。
補助金活用や事業計画づくりに関するご相談は、当事務所にて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
補助金お問い合わせフォーム
通常の会計処理と圧縮記帳を利用した具体的な計算例は?
ここでご紹介する内容は、あくまで一般的な制度の仕組みです。
実際の税務処理については、企業の状況によって判断が異なるため、必ず顧問税理士等にご確認ください。
1億円の設備投資をし、5,000万円の補助金を受け取った場合について、
通常の会計処理と、圧縮記帳を利用した場合(直接圧縮法を使用)の会計処理 について見ていきます。
通常の会計処理

減価償却費は定率法償却率0.25で計算(10,000×0.25=2,500)
収入が1億円(補助金5,000万円と別に5,000万円の収入があるとする)だと、利益は 7,500万円です。(10,000ー2,500=7,500)
税金は利益 7,500万円に対してかかります。
圧縮記帳を利用した場合の会計処理(直接圧縮法)

減価償却費の計算(定率法償却率0.25)
(10,000-5,000)×0.25=1,250
収入が1億円(補助金5,000万円と別に5,000万円の収入があるとする)だと、利益は3,750万円 です。 10,000-5,000(圧縮損)-1,250(減価償却費)=3,750
税金は利益3,750万円に対してかかります。
税金のかかる対象となる金額が、通常だと7,500万円に対して、圧縮記帳を利用すると3,750万円となり、額が小さくなっていることがわかります。
これにより税負担を減らすことができます。
圧縮記帳の注意点とデメリットは?
- 補助金全額に適用できない可能性も
補助金の種類や用途によっては、圧縮記帳が適用できないケースもあります。
例えば、コンサルティング費用として受け取った補助金には適用できず、固定資産の取得に充てた場合のみ認められます。 - 税金を完全に免除できるわけではない
圧縮記帳は課税の繰延べに過ぎず、将来的に税負担が発生する可能性があります。 - 会計処理が複雑になる
圧縮記帳の適用には正確な仕訳処理が必要となり、税務申告の際にも専門的な対応が求められます。今回は、直接圧縮法を例に挙げてますが、「積立金方式」というものもあり、会社の状況に合わせて処理をする必要があります。
そのため、税理士や会計士に相談しながら適用するのが望ましいでしょう。
圧縮記帳を適用できる補助金は?
圧縮記帳が適用できる補助金は、基本的に「特定の資産の取得や改良に充てることが義務付けられている補助金」に限られます。 具体的には、以下のような補助金が該当します。
- ものづくり補助金 ▶ものづくり補助金に関するコラム
- 小規模事業者持続化補助金 ▶小規模事業者持続化補助金に関するコラム
- 事業再構築補助金 ※事業再構築補助金は終了しています
また、新事業進出補助金、成長加速化補助金、大規模成長投資補助金についても適用できる可能性があります。
まとめ――圧縮記帳を適用して負担を減らしましょう
補助金を受け取ると、そのままでは税金がかかることになります。しかし、圧縮記帳を活用すれば、 税金の負担を抑えることができます。
補助金の種類によって適用できるケースとできないケースがあるため、適用可能な補助金をしっかり確認し、 専門家と相談しながら適用するのが望ましいです。
補助金を活用する際は、税理士や会計士に相談しながら圧縮記帳を適用し、賢く税負担をへらしましょう。
本記事は制度の概要説明にとどまるものであり、個別の税務判断を行うものではありません。
実際のご利用にあたっては、税理士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
※税制の詳細な適用可否については税理士へご確認ください。